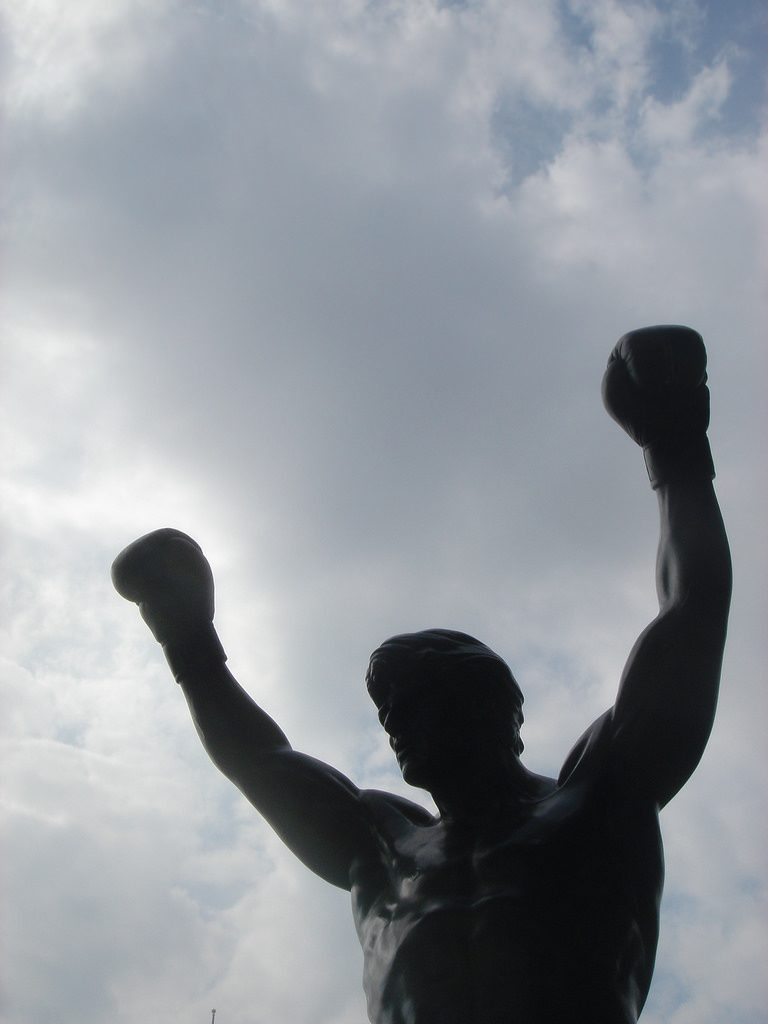以前、バスの免許取得については、こちらの記事【大型二種免許】運転免許センター(試験場)で最も安く免許取得した全記録【飛び込み試験】で、免許取得の流れやその方法について解説しましたが、今回はさらに深掘りし、試験場(=教習所)での”走り方”、つまり”テクニック”の部分について、詳細に、そしてとことん語っていきたいと思います。
お得情報!
実は試験場 (教習所) には、”試験場の”、”合格するための” 走り方というものが存在しています。
したがって、それを ”知っているか・知らないか” によって、試験場であれ教習所であれ、合格の確率は大きく変わってくることになるのです。
あなたも今回の記事を参考に、そうした「”受かる” テクニック」を身につけ、そしてそれを本番で発揮して、ぜひ、最速・最安での免許取得を実現してもらえたらと思います!
それではさっそく参りましょう!
ポイント
もちろん、「試験場」と「教習所」は “同じ基準” で運転技能の判定を行っていますので、今回ご紹介する内容は、「試験場」「教習所」どちらでも通用するものです。
参考
なお、今回ご紹介する方法は、私が実際に試験場にて行われる一発試験で大型二種免許を取得したテクニックに間違いはありませんし、私が保有する全ての免許は(ちなみに私は全免許制覇しています!)、実際にこの考え方で合格を勝ち取ったのですが、私自身「教習指導員」の資格も「技能検定員」の資格も持っていないため、100%確実と言えるものではないということを予めご理解ください。
「法規走行」とは
まず、試験場での一発試験でも、教習所での卒業検定でも、”技能試験” に合格するためには、”試験場用(教習所用)の走り = 合格するための走行法”というものが存在します。
これを一言で言い表すならば、「法規走行」ということになるわけですが、実際にはどのような走り方のことを言うのでしょうか。
一般にこれを最もイメージしやすいのは、「白バイの走り方」ではないかと思っています。

白バイ隊員の走りというものを長時間まじまじと観察したことのある方は少ないかとは思いますが、その特徴は「メリハリの効いた走り」とも言うべき、キビキビとしたものです。
”法規走行” と聞くと、1つ1つの確認動作を確実に行い、ゆっくり・丁寧に走るといったイメージを持つ人もいるかもしれませんが、これは半分正解で半分間違いです。
では、何が間違いなのか。
公道を走る際の状況を想像してみてください。自分が車やバイクで公道を走っている際に、周りの状況、環境に関係なく、ゆーったりと確認をして、ゆーったりと進む他の車などがいた場合、かえって危険になる場合もありますよね。
このような走り方は、技能試験の試験官的に言うならば、”流れに乗っていない”とうことになり、実は、試験場での技能試験でもこの点は結構重視されています。
つまり、「右左折時の ”寄せ”」や 「指示器を出す”タイミング”」、「確認の仕方」など、いわゆる法規走行が完璧にできていたとしても、「(その車両に)乗れていないな。」と試験官に判断されてしまえば、合格させてはもらえないのです。
これは考えてみれば当然です。
先ほどお話ししたように、確実に確認等は行えるものの、公道で周囲の通行に逆に危険をもたらしてしまうような運転者を世に放ってしまうわけにはいきませんからね。
まとめると、試験場での技能試験の際に求められる走り方・運転方法というのは、
”確認” や ”指示器の出し方” といった「法規走行」の基本となる所作が完璧であることを大前提とし、その車両に”乗れている”ということが試験官にも伝わる走り方
ということになります。
そうなると今度は、「じゃあその ”乗れている” って、どんな状態だよ。」と思われる方も多いかと思います。
![]()

これは、その試験車両(普通免許ならその普通自動車、自動二輪免許ならそのバイク、大型二種免許なら試験車であるバス)をしっかりと操れているかどうか、車両感覚が身についているかどうかということです。
つまり、バスの場合で言うと、そもそもシフトやクラッチ操作を考えながらやらなければならないようなレベルでは、周囲の安全に気を配ることができなくなってしまうわけですし、右左折時の内輪差や後方のオーバーハングに意識を向けることも難しくなってしまいます。(詳しくは後述)
”乗れている状態”というのは、その車両を動かすということにおいては、ほぼ ”無意識下” でできている状態、と言い換えることができますので、そこを目指さなければなりません。
技能試験を受けているその対象車両を、あたかも ”自分の手足のように” 操ることができている、そんな状態になれて初めて、確認作業等に重きを置いた、流れに逆らわない安全運転が可能となるわけです。
ご理解いただけましたか。
もう一度言います。
試験場で必要とされる “合格するため” の走行法というのは、それぞれの免許種別に応じた試験車両を、しっかりと乗りこなせている状態というのがすべての出発点になります。

そうやって、あたかも自分の身体の一部かのようにその車両を乗りこなせた上で、必要な個所で、必要な確認の動作や指示器の操作ができていてはじめて、試験場で「合格」がもらえる走りになるわけです。
この 「”車両感覚” をどれだけ早く掴めるか」ということ、これこそが何回目の試験で合格できるのかということに直結してくる部分にもなりますので、まずは自分がバスという車両の車両感覚をどこまで持てているか、そこをチェックしてみてください。
もしもこの感覚に自信がないようであれば、試験場であれば一発試験にいきなり飛び込む前に、どこかで練習ができる場所を探し、しっかりと感覚を掴んでから試験に挑んだ方が結果的には合格までの時間的、経済的コストは安く抑えることができるかと思いますし、教習所であれば、この車両感覚というものを意識して練習をすれば、合格はグッと近づいてくると思います。
少々長くなってしまいましたが、技能試験合格には、この点は非常に大切なポイントとなりますので、これをまず理解した上で、ここからの細かな ”お作法” について確認していってもらえたらと思います。
『大型二種免許』技能試験”合格” のためのバスの運転の仕方

試験開始
さて、いよいよ試験のスタート時間を迎えると、試験場一発試験では、まずはバスの発着点付近の待合室にて技能試験の開始時刻まで待機することになります。
そして、試験官の事前準備等(車両を出したり、試運転したり)が済むと、待合室にて試験官から試験の内容について簡単な説明があり、質問の時間などが設けられます。
それが完了すると、その日の受付順に試験がスタートしていきます。
ワンポイント
試験の順は、基本的には試験日当日の”受付順”となります。したがって、あらかじめ試験コースのコース表を入手しておき、自分は後半のコースの方が得意だとか、その日の試験官の癖などを他の受験者の様子を見て観察したいといった場合には、なるべく受付時間終了間際に受付を行うようにしましょう。そうすることで自分の受付順を最後の方へもっていくことができ、結果的に試験順も後の方にすることが可能になります。
いよいよ試験がスタートすると、バスへ乗り込み、運転席へ座ります。すると試験官から氏名などを確認されますので、口頭で回答します。(稀に確認を行わない試験官がいたりと、この辺りはバラつきがあります。)
試験官から「準備してスタートしてください。」という旨の指示がありますので、そこからスタートのルーティンを開始します。具体的には、
- 座席の調整
- シートベルト
- ルームミラーの調整
という順になります。
まずは、クラッチを踏み込んだ状態が自然となるように座席を調整し、シートベルトを締めます。次にその位置で社内が見渡せるようにルームミラーの角度を調整しましょう。
これが完了すれば、ギアがニュートラルに入っていることを確認し、フットブレーキを踏んで、エンジンをかけます。試験の順番等にもよるのですが、2番手以降である場合、先に受験した受験者が、停車の際に”バックギア”に入れているという場合もありますので、エンジンをかける前に必ずニュートラルを確認しましょう。
さらに、バスの場合、エンジンをかける動作が少し特殊です。
「補助スイッチ(または「メインスイッチ」)」というものが通常ハンドルの右下あたりにあり、このレバーを回しながら押し込むことでエンジンをかけることができるようになります。
メインスイッチをオンにすれば、あとは通常通りキーを回せばエンジンがかかりますので、慌てずに行いましょう。
ポイント
ちなみに、エンジンのかけ方は試験の内容、採点項目とは関係ありませんので、最初は解らなければ試験官に素直に質問して大丈夫です。
発進時のルーティン
続いて、発進時の確認動作についてですが、これは試験中全ての発進で必要となる動作ですので、普段から何度もイメージトレーニングをし、体で覚えて自然にできるようにしておきましょう。
上記のエンジンをかけるまでの動作が完了すれば、一言試験官に「始めますよ。」という自分の意思表示の意味も込めて、「よろしくお願いします。」と宣言します。
そして、発進時には、
- チェンジ
- サイド
- 指示器
という流れをルーティンとして ”3点セット” で覚えてしまいましょう。
毎回、発信の際には、すべてこの3点セットを1つの流れとして行います。
クラッチを踏んでシフトを2速に入れたら(この動作をここでは「チェンジ」と言います。)、サイドを下ろして指示器を出します。そして、前進時であれば、左右の死角(自分の左右45度後方)を目視で確認し(首振り)、ルームミラーで乗客の状態を確認します。(試験ですので、当然乗客はいませんがルームミラーでしっかりと車内を確認したという動作を行います。試験官から見て「確認していない。」と判断されてしまうと、確認不足で減点となってしまいますので、試験官からも判りやすいようにしっかりと目視するように気を付けましょう。)
後退時(バックの際)であれば、しっかりと首を振って振り返り、目視にて左右後方を確認します。
ここまでが完了して初めて、動き出します。後述しますが、発進時の”ショック”にも気をつけましょう。
通常走行時
確認作業を流れに沿って完璧に行い、発進ができれば、次は「通常走行」です。
通常走行時とは、普段真っすぐに走っている時や、カーブを走行する際のことですが、以下の点に気を付けて走行することになります。
白線
そもそも”白線”は基本的には踏んではいけないと考えておきましょう。
試験場内でも、路上試験(公道を走る本免許試験)でも、走行車線内を白線を踏まずに走る必要があります。
試験場内では当然のことながら、公道での試験においても、試験コースとして指定されている道路では、基本的には白線を踏まずに走行できるよう設定されていますので、まずはそこを意識してください。
しかしここで、「ん!?」と引っかかった方もいるかもしれません。
これは二種免許の筆記試験にも出てくる項目で、一点留意しなければならない事があるのですが、あなたは解ったでしょうか?
それは、白線の ”例外” です。
つまり、歩道側の線については、歩道のある場所の白線は右左折時に踏んでも構わないということになっていましたよね。
本免許(本試験)で路上を走る際には、歩道のある場所とない場所が入り混じっています。したがって、踏んで良い線と踏んではいけない線を見極めて走行する必要があるのです。
さらに、路上走行時において、たとえ歩道のある交差点を左折する場合でも、白線の内側にある路肩(地面の色が変わっている、走行車線と歩道の間の細い部分)を踏んでしまってはいけません。ここを踏んでしまうと「脱輪」で試験中止となってしまいますので、こちらも特に気をつけて走りましょう。
一方で、場内(仮免許の試験)の場合は、基本的には歩道は設置されていませんので、どの線も踏んではいけないということになります。
この「『踏める線』と『踏めない線』がある」という事を認識しておく事が大切です。
路上試験が不安な方は、事前に実際のコースを自家用車等で走って確認してみられるのが良いでしょう。
実際、私も何度も自家用車で試験コースと同じルートを走行して確認をして、本試験に臨みました。
通行位置
次に通行する位置ですが、基本的には走行車線の左寄りを意識した方が無難かと思います。この点については、私も不安があったので一度試験官に確認したことがあるのですが、その答えは「試験中ずっと一貫した走りをしてくれれば良い。」という回答でした。
つまり、最初から走行車線のど真ん中を走っていくのであればずっと真ん中を、左寄りを走るのであれば左端を走ってくれということです。要は、走行中にフラフラとすることが最も危険だという判断なのではないかと思います。
ここで思い浮かぶのが「キープレフト」ではないでしょうか。通常正しい走行方法とされるのは、キープレフトと言われる、なるべく走行車線内の左寄りを走る走り方です。
理屈で考えれば当然ですが、左寄りを走ることで対向車との接触のリスクを軽減できるとともに、歩道との間に二輪車が入り込むといった危険性についても事前に予防できますからね。
しかしバスの場合は、車両の幅が非常に大きな車両となりますので、そもそも走行車線の白線内に車両を収めるだけでもギリギリといった道も存在します。
そのため、試験官によってここは判断が分かれる部分というのが実感です。
一度、キープレフトについて試験官に尋ねたことがあるのですが、その試験官は、「キープレフトを意識した走りをするのであれば、試験中はずっとキープレフト。真ん中を走るのであれば真ん中を走る。と、一貫した走り方をしたほうが良い。」と言われました。
つまり、”一貫した” との言葉からも、要は、フラフラした走りをしていると減点対象となる可能性がある、といった意味合いのことが伝えたかったのだと思います。
私は「キープレフト」を意識して走行していましたが、ここはあなたの好みと試験官の考え方次第ということになろうかと思います。
横断歩道
路上試験の通常走行時には、横断歩道にも気を付けましょう。
横断歩道付近に歩行者がいて、渡るのか渡らないのか判らない場合は、一旦停止するのが無難です。同乗する試験官が、その歩行者が横断歩道を渡ろうとしていると判断した場合、”歩行者妨害”によって”試験中止”となってしまいます。
実際に私も一度これで試験中止となったことがありました。歩道のすぐそばを歩く人がいることは当然認識してはいましたが、この時私は横断歩道を渡る意思はないと判断し、徐行ではあるものの一時停止することなく進みました。そして、自分では合格したと思った試験終了後、試験官から歩行者妨害を指摘されたのです。気を付けましょう。
ショック
続いては ”ショック” についてです。
このショックとは何かというと、発進時、停止時、クラッチミート時のショック(大きな揺れ)のことになります。
大型二種免許では、乗客を安全に目的地まで運ぶという責任、義務が生じますので、走行時のショックによって乗客に転倒等によってけがなどをさせるわけにはいかないわけです。
したがって、路上での一旦停止や、クラッチ操作の際に車体が大きく揺れたりといったショックを与えてしまうと、それがあまりにも頻繁にあるようであれば、試験では減点とされてしまいます。また、乗務中であれば事故につながる可能性もあるということになってしまいます。
アクセル、ブレーキ、クラッチ操作の際には、なるべくショックが少なくなるようなスムーズな走行を心掛けるようにしましょう。
確認
直線道路を通常走行している時の確認についてですが、主に「交差点侵入前」と、「横断歩道」には気を配り、左右を確認するようにしましょう。
信号無視の車両などに気を配るということと、先程も触れましたように横断歩道を渡ろうとする歩行者等は優先ですので、道を譲る必要があります。
右左折時

通常走行時の注意点についてはご理解いただけましたでしょうか。真っすぐ走っているだけ、カーブを曲がるだけ、でも気を付ける場所がいっぱいですよね。
私も初めてそれらのことを意識して走った際には、やることが多すぎて受かる気がしませんでしたが、だんだんとそのような走行方法が身についてくれば自然にできるようになりますので、イメージトレーニングに励んでいただければと思います。
それでは続いて、右左折時の注意点について説明していきたいと思います。
交差点進入前
まず右左折をしようとする交差点に向かう時点(交差点侵入前)ですべきことですが、
- 「交差点の30m手前で、指示器を出す」
- 「指示器を出した3秒後に、後方確認」
- 「後方確認後、曲がろうとする側の白線へ車体を寄せる」
という順になります。
特に 2. の ”3秒後” というのは、私が実際に試験官に指摘された項目ですので、注意してください。
初めは「確認なんて、とにかくしまくっていれば文句はないだろう。」と言わんばかりに、指示器を出す前から出した後から曲がり始めから、首を振りまくっていたのですが、そうなるとこの”3秒後”の確認というのを外してしまう時があるんですね。
むやみに首を振りまくるのではなく、しっかりと適切なタイミングで、必要に応じて確認を行うということを、基本に忠実に行うようにしてください。
そしていよいよ交差点に進入していくのですが、信号や一旦停止の停止線で止まった後であれば、通常の発進時のルーティンである、左右後方と車内の確認を済ませてから、さらに交差点の確認を行って発進します。
その際、まず前提として、最大限の徐行で侵入するようにしていきましょう。法的にも、交差点右左折時にには”徐行する”と規定されていますので、むやみに速度を出して曲がってはいけません。
私は最初の頃勘違いをしていて、いわゆる”乗れていますよ”という車両感覚をアピールするために、ある程度のスピードを保持したまま右左折するようにしていたのですが、結論としては「最徐行」が正解です。この ”スピード” についても、右左折時には気を付けるようにしましょう。
交差点に差し掛かると、まず交差点内を首を振って確認します、その際注意すべきポイントは3点あります。
まず1点目は、「対向車」。これは、右折の際ということになりますが、対向車の途切れた切れ間に自分が曲がり切れる間合いを図ることになります。この際、自車が曲がり切った後、向かってきていた対向車が減速せずに直進できるだけの間隔が空いていれば曲がることができるという判断になります。言うまでもありませんが、バスというのは非常に車体が長い上に、ゆっくりと曲がっていく事になりますので、十分に余裕を持って右折を開始するようにしてください。
自分(こちら)が右折している最中に(車両後方が対向車線に残っている状態で)相手がすぐ近くにまで迫って来ていて、スムーズに直進できず減速してしまったら、それは減点となります。対向車の車間のちょっとした隙間を縫って曲がるといったことはせず、十分すぎるぐらいに間隔を空けて曲がり始めるようにしましょう。試験官が「危ない。」と感じてしまえば、その時点で有無を言わさず減点です。
曲がり始めたら、2点目の注意ポイント、「歩行者の確認」です。通過しようとする横断歩道に歩行者がいないか、横断しようとしている歩行者はいないかを確認します。この時、自分(バス)が横断歩道上を通過している間に歩行者が待たなければならなくなる可能性がある場合は、歩行者が渡り切るまで待ちましょう。
そして3点目は、「後方オーバーハング」です。
これは一般に”ケツ振り”と言われるものですが、例えば右折レーンのある交差点で、自分がその右折レーンから右折しようとする場合、自分の左側の車線に車がいることもありますし、自分が右折中に後ろから別の車両が迫ってくることもあるでしょう。
この別の車両というのは、自分(バス)が右折しようとすると同時に、バスの左側を追い抜いて直進していくことになります。その時、右に曲がり始めたバスの左後方タイヤより後ろの部分(この車体部分をオーバーハングと呼ぶ)が左側の車線へ出てしまうことがあるのです。
このオーバーハング幅というのは、バスがどういう曲がり方をするのかによっても変わってくるのですが、急ハンドルを切って曲がる、つまり、直角に近い形で曲がるほど、オーバーハングは大きくなります。(12mバスであれば、最大 70cmとされる)
このオーバーハングによる左車線を走行する車両への接触を意識しておく必要があるのです。
ここで一つ矛盾が発生するのですが、それは何でしょうか。
基本動作としては、右折の場合であれば、信号が変わればまず交差点の中にある中心点を狙って前進し、その”すぐ”内側を左前輪が通過するように曲がっていくわけですが、交差点を曲がった後に、自分が侵入しようとする車線の対向車線に信号待ちの車がいて、その車がかなり前に出た状態で待っていた場合、自車(バス)は右後輪の内輪差でその対向車にあたってしまう可能性があるため、大回りして、直角に近い形で回っていく必要があります。しかし大回りすると、今説明したように、左後方のオーバーハングで元の車線の直線車線にいた車に左後方部をひっかけてしまう可能性があるわけです。
つまり、交差点を曲がる際には、自分が信号待ちをしていた車線を直進しようとする自分の後続車に後方のオーバーハングを引っ掛けないように気を付けると同時に、中心点のすぐ内側を沿って走り、さらに入って行こうとする車線の対向車に内側の後輪を内輪差で接触させてしまわないよう気を付けて曲がっていく、ということになるわけです。
左折の場合も基本的な要領は同じですが、左折の場合は「巻き込み確認」も必要です。右折時には、運転席から綺麗に自分の右側が見えるのでまだわかりやすいのですが、左折時には、左斜め後方45度の位置の死角に自転車や歩行者が入り込んでしまうことがありますので、細心の注意を払いつつ曲がっていくようにしましょう。
これで交差点での右左折時の注意点は以上です。
交差点を曲がるというだけで、これだけのことに注意を払う必要があるわけですね。文章で表現すると必要以上にややこしく感じてしまうのですが、実際に体を動かし、順を追って手順をなぞってもらえればわかりやすいかと思います。ここでもぜひイメージトレーニングで感覚を身に染み込ませていくようにしましょう。
特に路上試験の際には、道路状況は刻一刻と変化していますし、どんな通行人がいるかもわかりませんので、細心の注意を払って運転する必要があります。
試験官は、あなたが思っている以上に心理的な恐怖を感じているものです。もしもあなたが見落としたポイントがあり、試験官が「危ない!」と感じてしまったら、試験官に緊急ブレーキを踏まれてしまい、試験は即中止、終了です。
そうなってしまわないためにも、一連の流れを是非”体”に叩き込んでおきましょう。
試験課題
ここからは、通常走行を離れ、クリアしなければならない「試験課題」についてみていくことにしましょう。
試験課題は、仮免許の取得を目指す場内での試験時と、本免許取得を目指す路上試験のそれぞれに分かれて課されますが、ここでは全てを順に解説していきたいと思います。
路端停止
まずは、「路端停止(ろたんていし)」です。
これは場内試験でも路上試験でも、つまり、仮免許でも本免許でもどちらの試験でも必要になる課題です。早い話が、「バス停での停止」を想定したものですね。
目印となるポールや標識に合わせ、左側の縁石30cm以内に寄せて止まる技術を見る試験になります。
場内試験では、左前方にあるポールに左前のAピラーを30cm以内に合わせる。路上試験では、試験官に指示された場所で計3回程度、後方ドアを指定された対象物の標識や電柱に合わせる形で行われます。
手順は、まずその対象物となるものから30m手前で左指示器を出し、左後方を確認します。そして半クラの超低速で路肩へ寄せていき、しかるべき位置で停止、ニュートラルに入れて、サイドを引き、試験官に「完了しました。」と宣言して完了です。この時、フットブレーキから足は離さず、ブレーキは踏み続けるようにしましょう。
さらに場内試験においては、路端停止から抜け出す際、停止位置から前方3mほどの位置に、壁に見立てたポールが設置されていますので、これを右に交わして抜け出す必要があります。
これは簡単で、路端停止完了から発信する際に、停止状態からハンドルを一回転右へ切って抜け出ていけばクリアできます。右一回転で綺麗に抜け出せますが、切り方が甘くて左の前を障害物にひっかけたり、切りすぎて左後方のオーバーハングを引っ掛けてしまったりしないように気をつけましょう。
あい路
これは、場内試験での課題になりますが、徐行での直進している状態から、一度も止まることなく、徐行のまま90度曲がった状態に持っていき、その先にある白線の枠内に入れるという課題になります。
白線内に収まらなかったり、斜めに止まってしまった場合には、2回以内で切り返して修正をすることは可能で最終的に枠内に収まれば大丈夫です。
踏切の通過
これは普通車の時と同じで、踏切手前に来たら一時停止し、窓を開けて音を確認します。そして踏切音がなくなったことが確認できれば、発進します。この時、バスの車体が完全に踏切内から出るまではシフトチェンジをしてはいけません。発進時に入れたギア(基本的には2速)のまま、一気に通過してしまいましょう。
サイド合わせ(坂道発進)
これも普通車と同じ要領です。坂道の頂上付近の停止線手前で一旦停止し、サイドを引いたら一旦ブレーキから足を離します。ギアを1速に入れた後、発進時の確認を行い、半クラにしたら、サイドを下げながら発進します。
発進したらその先が下り坂になっていますので、1速のまま、エンジンブレーキを利用して下り坂を下りましょう。これで完了です。
Sコース
これは進入時に一旦停止の必要はありませんので、対向車がいなければ、徐行のまま侵入し両サイドのポールに接触しないようにS字カーブを抜ければOKです。
ポイントとしては、基本的には曲がる方向の反対側、外側のミラーを障害物ギリギリに沿わせていけばまず間違いなく他のポイントが接触することはありません。要は内輪差での脱輪に気を付けていれば大丈夫です。
障害物の通過
これも普通車と同じで、障害物の手前で指示器を出して確認をし、障害物を交わしてすぐにまた元の車線へ戻るために指示器を出して確認をし、元の車線へ戻るというものになります。
この時、大型車は車体が長いですので、元の車線へ戻る際に左後方を引っ掛けてしまわないように気をつけましょう。
50キロ走行
これも何も難しくはありません。しっかりと50キロの速度が出せていて、車両がふらつくことなく走れていれば大丈夫です。大型車は車体特性上、高速走行時に車体の挙動が不安定になる場合があり、横風の影響も受けやすいですので、なるべく遠くを見ながら安定走行するように気をつけましょう。
また、時速50キロ走行指定の終了の標識を超えて50キロ程度スピードが出てしまっていては、速度超過となってしまいますので、これも見落とさないようにしましょう。
方向変換(Uターン)
方向変換も基本的には普通車の時と同じですが、コツをお教えしておきます。ここでは、自分の左側にバスの車体後方を入れて方向変換するというパターンを前提とします。
まず方向変換のポイントに到着したら、車線左端から車体までの間隔を50cm程空けて止まります。そして、自分の進行方向の先に3つの点が並んでいると思いますので、そのポイントと自分の前のダッシュボードの上部あたりが大体重なる程度まで前進します。
そこで止まったら、右いっぱいにハンドルを切って前進します。脱輪しない程度まで前進したらストップし、今度は左いっぱいにハンドルを切ってバックします。この時、バックしている最中に右前輪が出過ぎて前側に脱輪してしまわないよう右ミラーで確認し、ハンドルの切れ角を調整しながら下がるようにします。
そのままゆるやかにハンドルを戻しつつ下がっていけば、あとは勝手に車体が方向変換用のスペースに収まりますので、入ったら元来た方向へと抜け出せればOKです。
バックしてスペースに収まった段階で、試験官に完了の合図をする必要はありません。方向変換が完了した時点で試験官から何かしら次の指示があるはずですので、それを待ちましょう。
後方感覚
正直、課題の中ではこれが最も難しいかもしれません。
課題の内容としては、単純に真っすぐバックし、後方に設置された障害物にみたてたポールから50cm以内に車体を止めるというだけのことなのですが、何せ運転席から車体後部の端が非常に遠いですので、最初は感覚的に非常に難しいかと思います。
いわゆる深視力と車体感覚を見る試験ですが、50cmというのは想像以上に至近距離です。感覚的にはもう当たっています。
なお、この試験は後方が障害物に接触してしまうと一発で中止になってしまいますので、自分が「ここなら絶対に当たらない」と思う感覚で限界まで下がり、停止したらそこで完了した旨申告しましょう。試験官はバックカメラで見えています(当然自分は見えません。)ので、完全にクリアしていればそのままOKとなり、微妙な距離が残ったら試験官がメジャーを持って距離を計測に行きます。
そこでまだ距離が足りていない(50cm以上離れている)と、再度やり直しとなりますのでもう一度チャレンジしてクリアできればOKです。やり直すチャンスはありますので、とにかく接触はしないように気を付けることと、やり直しの時のために1回目の距離感はできれば覚えておくようにしましょう。
縦列駐車
これも要領は普通車と同じですが、バスで行う際のポイントについてお話していきます。なお、この場合も縦列駐車をしようとするスペースが左側にあるということを前提として進めます。
まず駐車するスペースを少し通り過ぎ、左後方のドアが駐車スペースの枠の前方側のポールを超えた辺りで止まります。左側は決まった距離感はありませんが、50cm程度空けておけば大丈夫です。
そして左にハンドルをいっぱいに切ってからゆっくりとバックし始めます。右のミラーで確認をしながら、車体の右側面の後方延長線上に縦列駐車の枠の左後方の角のポールが見えたら、ハンドルを真っすぐに戻します。
そのまま真っすぐに、バスの右側面の延長線上に縦列駐車の枠の左後方角のポールがある状態で下がります。
そしてバスの左前のAピラーが、縦列駐車の枠の右前方のポールを超えた時点でストップし、今度は右いっぱいにハンドルを切ります。そこからそのままバックすれば、車体が縦列駐車の枠内に収まってくれます。
枠内に収まれば、ハンドルを真っすぐに戻す必要はありませんので、そのままサイドを引いて、試験官に完了した旨を報告すればOKです。
鋭角
最後に鋭角の方法について説明します。これは、左に鋭角を曲がっていくということを前提に説明したいと思います。
鋭角も、S字と同じく、手前で一旦停止する必要はなく、そのまま車体の右側を鋭角コースの進入車線の右側に沿わせるように進みます。
そして、バスの前方部を確認する”丸ミラー”で、車体前方についているウィンカーレンズの部分が鋭角コースの前方の端に差し掛かった所で左いっぱいにハンドルを切ります。
そのまま前進し、脱輪せずに行けるギリギリの所まで来たら一旦止まります。そして今度は右いっぱいにハンドルを切った状態でバックします。右前のウィンカーレンズが鋭角コースの端に差し掛かったらストップします。そしてまた左にハンドルを切りながら前進し、右前のタイヤの脱輪、左後タイヤの乗上げに注意して進みます。
通常は一度の切り返しでクリアできますが、場合によってはもう一度切り返すか、ハンドルの切れ角で修正舵を打ちながら進むようにして下さい。
この鋭角での注意点は、鋭角の中心部分から外側に向かって若干坂になっている場合がありますので、切り返しで発信する際に車体が下がってしまわないよう、しっかりと半クラの状態を自分で感じてから発信することです。
そしてこれはバス特湯の特徴と言えるものですが、実際に曲がっている最中は、自分(運転席部分)は車線からはみ出ています。もちろんこれはOKで、前タイヤよりも前に運転席があるバスだからこそ起きる現象です。
おまけ:私が試験で指摘された事項
最後に、私が実際に試験を受けた際に試験官から指摘された事項について補足をしておきたいと思います。
試験官の生の声、どこを気にしてチェックしているのかといった感覚を知るという意味で参考にしていただければと思います。
停止位置
まずは、停止位置です。路端停止の課題において、合格基準(減点対象にならない)としては、バス後方にある乗降口(ドア)の範囲内に対象となるポールが収まっていればOKなわけですが、実際には結構シビアにチェックされます。
私は2度程これがずれていて減点されてしましました。深視力にも関係する課題ですが、試験前などにあらかじめ確認して感覚を身に付けておくことをおすすめします。
指示器の出し忘れ
これは方向変換の際にやってしまいました。
脱輪や接触にばかり気をとられ、方向変換後の発進の際に指示器を忘れてしまったのです。発進時には、常に「チェンジ、サイド、指示器」のルーティンを行いましょう。
速度不足
これは路上試験の際ですが、制限速度が60キロの見通しの良い幹線道路で言われてしまいました。速度が足りていなかったのです。
試験前から、制限速度から著しく速度が低い状態で走っていると減点となるということは認識してはいましたし、その時の状況も、そこまで60キロギリギリまで速度を出す必要もないだろうと、50キロ前後で走行していて注意されてしまいました。
「適切な速度で走行してください。」試験官にそう言われて、もちろんこれも減点です。
この辺りは”感覚”的なものなので、正直”運”の要素も大きいかと思います。試験官にとって「速度が足りていない。」と感じればそれで減点ですし、反対に制限速度ギリギリで走行するのが危険だと判断されるような状況であれば、危険運転で減点もしくは試験中止です。
基本的には制限速度ギリギリを出せる安全性が確保されていればそうしなければなりませんし、なにか危険性が予知される状況であれば減速する、という姿勢で臨むしかありませんね。
確認不足
これは、2パターンあります。
1つ目は、車線変更時です。交差点が2つ連続していて、2つ目の交差点を右折しなければならず、その手前で車線変更する際に、自分としては確認したつもりでしたが、試験官の理想とするタイミングではなかったらしく、これも減点されました。
もう1つは、交差点進入時です。大きな幹線道路を50キロ前後で走行中に、各交差点を通過する際の左右確認が甘いと指摘されました。どれだけ優先順位が明確な大きな幹線道路であったとしても、危険予測としての交差点左右確認は必要となりますので、カーブミラーの確認と併せてクセづけるようにしましょう。
ふらつき
これは、60キロ弱で走行中に言われたものですが、若干車体のふらつきを感じると言われました。これも試験官の感じ方次第の部分がありますので対策は難しいのですが、なるべく遠くを見つつ、微妙な揺れを発生させないよう安定した走行を心掛ける必要があると言えそうです。
まとめ
はい、以上となります。大変お疲れさまでした。
物凄く長々と、タイトル通り事細かに解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
文章にしてしまうと非常にややこしく感じる部分もあるかとは思いますが、私自身が合格するために必要と感じたことや経験したことは全てお話してきましたので、大型二種免許の取得を目指される際には是非とも参考にしてみていただければと思います。
それでは、安全運転で、行ってらっしゃい! Good luck!!